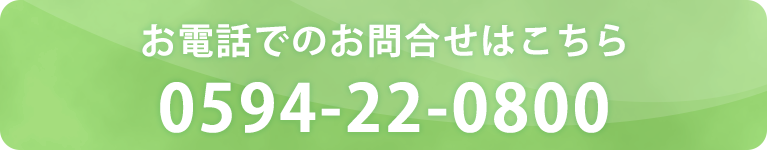内科・呼吸器内科・消化器内科・アレルギー科
医療法人社団桑久会 久瀬クリニック
三重県桑名市東方232
TEL: 0594-22-0800
当院の特徴
長引く咳や息切れなどのつらい症状でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。

● 気管支喘息について
長引く咳、繰り返す咳の原因は気管支喘息、咳喘息かもしれません。
気管支喘息とは気道内が炎症を起こしていることが原因でおこる病気で気道が狭くなっています。
炎症を起こしている気道に刺激(ホコリやストレス、温度や気圧の変化)が加わると、さらに気道が狭まり、息をするたびにヒューヒューやゼーゼーといった音が出るようになってしまいます。
そのため気管支喘息の治療は、吸入ステロイド薬で炎症をおさえることが基本となります。治療でいったん症状がよくなっても、気道内の炎症は残っているため、吸入ステロイドを続行し、炎症を抑え続けることが肝要です。
グラクソ・スミスクライン株式会社様のサイト「ぜんそく.jp」もご参照ください。
● お子様の長引く咳、小児喘息について
小学生以上の方に対応しております。咳が出始めて3週間以内の場合は、風邪やウイルスなどの感染症が原因であることが多いと言われています。
一方で3週間以上咳が続く、または咳が長引くことを繰り返している場合は、風邪以外の原因(喘息、アレルギー、鼻の病気など)が背景にあることが多いです。
気管支喘息であれば、悪化因子への対策を行いつつ、薬物療法になります。症状を認めない事、スポーツを含めて日常生活が普通にできることを目標に治療していきます。
● COPD、慢性閉塞性肺疾患について
いつも咳や喀痰がでたり、階段や坂道で息が切れるような方は、COPDかもしれません。COPDは日本語で「慢性閉塞性肺疾患」と呼ばれます。「肺気腫」とも呼ぶこともあります。
喫煙経験のある中高年の方に起こりやすい疾患です。肺の中にある肺胞が破壊され、呼吸によるガスの交換に異常をきたし症状が出てきます。
COPDのほとんどの原因はタバコですので、禁煙は治療の中で非常に重要で効果的な方法です。
また症状を緩和し生活の質を上げ、病気の進行を抑えるために吸入薬を使用することが多いです。咳や痰、息切れでお悩みの方や、長年タバコを吸っていて肺機能に不安のある方は、お気軽に当院までご相談ください。
アストラゼネカ株式会社様のサイト「チェックCOPD」もご参照ください。
睡眠時無呼吸症候群の診断、治療に力を入れております。

睡眠時無呼吸症候群とは、寝ている間に呼吸が止まっては再開することを繰り返す病気です。
この病気になると、夜間の睡眠が妨げられるため、日中の眠気や集中力の低下などの症状が現れます。
睡眠中に連日低酸素状態になるため、治療をせずに放っておくと、生活習慣病や血管・心臓・脳の病気のリスクが上がり、心筋梗塞や脳卒中で倒れてしまうこともあります。
このような症状はありませんか?
- 昼間にすごく眠くなる。
- 周囲の人にいびきが大きい、睡眠中に息が止まっていると言われる。
- 睡眠の質が悪い。熟睡ができない。
診察、問診を行ったうえで睡眠時無呼吸症候群の疑いがあれば、まずは小型の装置を自宅に持ち帰り、センサーを付けて睡眠中の呼吸状態などを調べます。
睡眠時無呼吸症候群の治療方法は複数ありますが、最も代表的で有効な治療法が「CPAP(シーパップ)治療」です。
この病気の診断、治療機器のメンテナンスに関してお世話になっているメディカルケア株式会社様のホームページはわかりやすいので、ご参照ください。リンクはこちら
症状に応じて、漢方薬の処方も可能です

以下のような方は漢方薬が役に立つかもしれません。
倦怠感、冷えなど漠然とした症状
症状があるのに、検査を行っても「異常なし」と判定される。
同時に様々な症状がある。
心身ともに調子が悪い場合
現在使用している西洋薬が多い場合、西洋薬で副作用が出たことがある場合
また感冒、気管支炎、新型コロナ罹患後の体調不良などにも有効なことが多いです。
アレルギー疾患全般の診療をしております。鼻炎に対する舌下免疫療法も可能です。
2025/9/8現在 スギ花粉症の舌下免疫療法に使用する薬剤「シダキュア」が大変手に入りにくくなっております。

●アレルギー性鼻炎、花粉症について
鼻アレルギー、鼻炎かなと感じたときは、放置せず受診しましょう。アレルギー性鼻炎は日常生活や喘息などほかのアレルギー疾患に影響を及ぼすこともよくありますので、治療をすることがとても大事です。
問診、採血検査にて原因となるアレルギー物質を特定しましょう。(アレルギー検査について詳しく)
そのうえで、じっくり相談のうえ、自分に合った治療法を選択しましょう。当院では鼻炎の治療と同時にほかの内科疾患の治療を行うことも可能です。
以下のような治療を行います。
1)アレルゲンの除去、回避、暴露軽減
2)抗アレルギー薬内服、点鼻薬で症状を緩和する治療
内服はたくさん種類があります。患者様の状況を伺い、効果の強さ、眠気のでやすさ、用法での使いやすさを考え、薬を選びます。
効果や、副作用の出方には個人差があります。使ってみて自分に合っており快適に過ごせる薬を探すのがよいでしょう。
点鼻は液体を1日1回点鼻するタイプが一般的です。最近は鼻への刺激が少なく、鼻の粘膜が過敏な状態でも問題なく使える粉末タイプの点鼻(小児には処方不可)も処方可能となっています。
3)アレルゲン免疫療法(=舌下免疫療法)
検査でスギアレルギーまたはダニアレルギーと確定した方に行うことができます。アレルゲンを含む治療薬を投与し、体を徐々にアレルゲンに慣らすことによって症状を和らげたり、根本的な体質改善が期待できる治療法です。
スギ花粉症に対しては「シダキュア」、ダニアレルギーに対しては「ミティキュア」または「アテシア」という薬を使用します。約6割の人がくしゃみ、鼻水、鼻詰まりなどの花粉症の症状が軽くなり、約2割の人は症状が出なくなると言われています。アレルギー治療薬の減量や生活の質の改善が期待できます。
しかし効果には個人差があり、効果が出ない方もあります。
通常治療期間は3〜5年にわたります。改善には、定期的な来院が必要で根気がいる治療です。
治療の流れですが、まず、舌下免疫治療の概要、注意点についてご理解いただき、1回目の内服の予定日を決めます。1回目の内服は院内で行います。服用後30分休憩していただき、副作用が出ないかを確認します。開始1週間後に経過を確認し、薬を増量します。
2週間後、4週間後に経過を確認し、問題がなければ、そのあとは月1回受診していただき、治療を継続していきます。